









各都道府県の行政書士








行政書士だから出来ること
行政書士は、あなたに代わって書類を「集めて作成し申請」することが出来ます。(行政書士ではないコンサルタントに依頼した場合は、あなたが「集めて作成し申請」することになります。)

また、保険加入の行政書士が対応いたしますので、行政書士が行った申請によってあなたが損害を受けた場合、あなたが保険料を支払うことなく保険が適用されることになります。
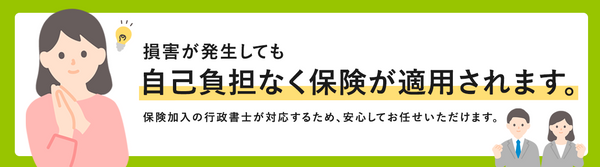
その他、ホームぺージの作成・事業計画書作成・法人設立・融資サポート・補助金サポートについても、それぞれの経験豊富な専門家がご案内いたします。
事業の開業と継続
行政書士は、国家資格を持つ専門家として、安全で信頼性の高いサービスを提供しています。開業やフランチャイズビジネスには、多くの成功のチャンスがある一方で、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
行政書士グループであるフクサポは、そうしたリスクを避け、安心してビジネスを進めることができます。事業の開業と継続を支援できることがフクサポの強みです。
開業までの流れ

事業成功のためのロードマップを示すものです。事業に関わったことのある専門家が作成することでリアルな計画になります。これは「融資」や「補助金」を受ける際にも使用されます。
「求人」や「融資」や「補助金」のために使用するホームページを作成をいたします。もちろん開業後には、「利用者の獲得」や「業務の獲得」のために使用いただけます。
あなたが主体となって、申請要件であるサービス管理責任者や、その他の求人を行います。
フクサポは、「ハローワーク」や「民間の求人サイト」への登録のアドバイスを行います。
あなたが主体となって、申請要件であるテナントの契約を行います。
フクサポは、テナントについてアドバイスを行います。
申請要件である法人(合資会社・株式会社)を、司法書士と共に設立いたします。
融資とは、国や銀行からの借り入れです。融資は返済が必要となります。有利な条件で借り入れできるように融資コンサルタントが最適なサポートを提供いたします。
就労継続支援A型とB型の多機能型(2つ以上の事業を同時申請)の申請を推奨しています。
おめでとうございます。事業者として指定されれば開業となります。開業後は運営コンサルとしてサポートいたします。
補助金とは、国や地方自治体からの資金援助です。原則的には、補助金は返済の必要がありません。補助金コンサルタントが、最適なサポートを提供いたします。
クラウドファンディングは、「資金調達」と「事業内容の広告」と「利用者へ与える作業」の3つを獲得することに役に立ちます。
他社とのサービス比較
★:得意分野
○:対応可能なこと
△:クライアント様が主体的に行う必要があること
–:対応できないこと
| 本サービス | コンサル | FC | |
|---|---|---|---|
| ①事業計画書作成 | ★ | ○ | ○ |
| ②ホームページ作成 | ○ | – | ★ |
| ③従業員の求人 | △ | △ | △ |
| ④テナントの契約 | △ | △ | △ |
| ⑤法人設立 | ★ | – | – |
| ⑥融資の調査 | ★ | ○ | ○ |
| ⑦役所へ申請 | ★ | ○ | ○ |
| ⑧運営コンサル | ★ | ★ | ★ |
| ⑨補助金の調査 | ★ | ○ | ○ |
| ⑩クラファン登録 | ★ | △ | △ |

サービスと報酬
| 本サービス | 合計 131万円 |
|---|---|
| ①事業計画書作成 | 20万円~お見積り |
| ②ホームページ作成 | 15万円~お見積り 月額 1万円 |
| ⑤法人設立 | 10万円~お見積り |
| ⑥融資の調査 | 着手金15万円目安 成功報酬15万円目安 |
| ⑦就労継続支援の申請 | 25万円~お見積り |
| ⑧運営コンサル | 月額 33,000円 |
| ⑨補助金の調査 | 着手金15万円目安 成功報酬15万円目安 補助金採択後のフォロー3万円目安 |
| ⑩クラファン登録 | 1万円~お見積り |

よくあるご質問
設立手続き・流れ
- Q就労継続支援事業所を設立するために必要な手続きと流れを教えてください。
- A
事業計画書を作成し、法人格を取得、人員配置や設備整備を行った後、申請手続きを行います。
- Q就労継続支援事業所の設立にはどれくらいの期間がかかりますか?
- A
一般的に6ヶ月から1年程度かかります。
物理的要件・設備
- Q就労継続支援事業所の設置基準や物理的要件(面積や設備)を教えてください。
- A
訓練・作業室(1名につき約2畳)、相談室、洗面所、トイレ、多目的室など、運営に必要な設備が必要です。
スタッフの資格要件・人員配置
- Q就労継続支援事業所のスタッフの資格要件、配置基準、雇用形態について教えてください。
- A
管理者(常勤)、サービス管理責任者(常勤・兼任可)、指導員・生活支援員(非常勤可)が必要です。利用者数に応じて適切な人数を配置します。例:利用者20名で4名以上の従業員が必要です。
- Q職業指導員と生活支援員は兼務可能ですか?また、どちらが常勤であるべきでしょうか?
- A
兼務可能です。どちらが常勤でも問題なく、特に差はありません。資格要件も必要ありません。
費用・資金調達
- Q就労継続支援事業所を設立する際の初期費用と運転資金の目安を教えてください。
- A
初期費用と運転資金は、1,200万円から2,000万円程度が目安です。
- Q就労継続支援事業所設立時の自己資産と融資の理想的な割合はどれくらいですか?
- A
自己資産は初期費用と運転資金の3割から5割が理想です。例:1,200万円なら360万〜600万円、2,000万円なら600万〜1,000万円です。
- Q行政からのサービス費は申請からどのくらいで支給されますか?
- A
支給までに約2ヶ月かかります。
補助金・助成金・税制優遇
- Q就労継続支援事業所設立時に利用できる補助金や助成金を教えてください。
- A
就労支援事業補助金などで、月額数十万円から数百万円の運営費や、新規開設時に数百万円から一千万円程度の設備費が支給されることがあります。
- Q就労継続支援事業所や障害者雇用に関する税制優遇措置について教えてください。
- A
障害者雇用促進税制(1人につき最大160万円の税額控除)や雇用安定助成金、事業所への支援があります。
法規・労働環境・契約
- Q就労継続支援事業所や障害者雇用に関する労働法規や労働環境の整備、労働契約について教えてください。
- A
労働基準法、労働契約法、障害者雇用促進法に加え、合理的配慮の提供、職場のバリアフリー化、安全衛生管理が必要です。
利用者対応・募集
- Q就労継続支援事業所の開業後、利用者や家族からどのような苦情やトラブルが発生する可能性がありますか?
- A
利用者やその親からの苦情が発生することがあります。対応できる環境作りが重要です。
- Q就労継続支援事業所の開業後、利用者の募集方法について教えてください。
- A
A型はハローワークが利用可能です。地域の相談支援事業所への挨拶や、ホームページ、SNS、YouTubeの活用も効果的です。
- Q就労継続支援の利用者はどのような方ですか?
- A
就労が難しい障害者の方が対象です。一般企業での就労が困難な方や、年齢・体力・病気などで就労が難しい方が利用できます。
- Q就労継続支援の利用者確保にあたり、障がいの種類を特定してもよいですか?
- A
はい、限定しても問題ありません。
- Q作業所は外国人も利用可能ですか?「日本人と結婚して働きたいが、思うように働けない」という理由の方も利用できますか?
- A
外国人も利用可能ですが、就労や長期滞在が認められる在留資格が必要です。また、障害者手帳や医師の診断書が求められる場合があります。
- Q利用者が1名の場合、開業時の従業員(支援員)の設置要件はどうなりますか?
- A
たとえば、横浜市では、初年度は定員の9割を満たす必要があります。要件は以下の通りです。①管理者とサービス管理責任者の兼任(常勤1名)②職業指導員と生活支援員の兼任(常勤換算で1.8名、うち1名は常勤)
運営方法・業務内容
- Q就労継続支援事業所の開業後、サービス提供内容や日常の運営方法について教えてください。
- A
パソコン作業をメインにし、他事業所にはない独自のサービスを提供することが重要です。今後は在宅作業の需要が高まると予想されます。
- Q利用者にリモートで業務を行ってもらうための要件は何ですか?
- A
リモート業務を希望し、効果が認められる場合に可能です。運営規程に在宅支援を記載し、開始前に区役所へ報告書を提出します。1日2回の連絡や進捗確認、月1回の訪問評価、緊急時対応が必要です。また、セキュリティ対策や記録の保存も求められます。
- Q開業後、職業指導以外にスタッフが行う事務作業にはどのようなものがありますか?また、専門知識が必要な場合、専門の事務スタッフを雇用すべきですか?
- A
事務作業には書類管理や報告書作成などが含まれます。専門知識が必要な場合は、専門の事務スタッフの雇用や、行政書士との顧問契約を検討することが有効です。
収益モデル
- Q利用者の労務からの利益を考慮しなくてもビジネスモデルとして成り立ちますか?
- A
はい、利用者を集めることで成り立ちます。
- Q基本単価は自治体によって変わりますか?
- A
はい、自治体によって異なります。例として、横浜市では1単位10.91円で、682×10.91=7,440円です。
- Q食事提供体制加算で1人あたり1日327円が加算されますが、これは食費が経費として計上されると考えてよいですか?
- A
はい、食費は経費として計上されます。ただし、加算額を超える食費がかかる場合、その差額は赤字になる可能性があります。近隣の飲食店と提携することで、コストを抑えることができます。
- Q生活保護を受給している方が就労継続支援で工賃をもらうと、生活保護費が減額されますか?
- A
はい、工賃は生活保護の「収入」として扱われ、一部は収入控除(月額2万円まで)が認められますが、それを超えると生活保護費が減額される可能性があります。
加算・報酬制度
- Q就労移行支援体制加算は、過去の利用者が6ヶ月以上就労継続している場合、現在の利用者全員に加算されるのでしょうか?
- A
はい、過去の利用者が6ヶ月以上就労し、定着した場合、現在の利用者全員に加算されます。これは非常に大きな加算で、一般就労へ移行することが重要です。
- Q就労移行支援体制加算は、就労移行支援施設だけでなく、就労継続支援B型の施設にも加算されますか?
- A
はい、B型から一般就労に移行した場合にも加算されます。就労移行支援やA型の併設は必要ありません。
法改正・更新情報
- Q就労継続支援事業所の開業後、法改正や更新情報について教えてください。
- A
法律や制度は3年ごとに見直され、報酬は毎年見直しが行われます。

